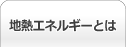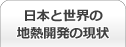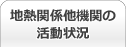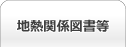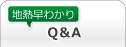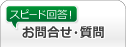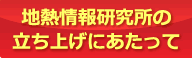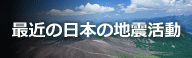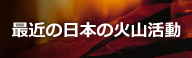『アフガンでハンセン病診療再開へ 中村哲さんの夢継ぐ ペシャワール会 技術伝承ラストチャンス』と毎日新聞2025年10月21日付朝刊 総合・社会面23ページは紹介している。
アフガニスタンなどで人道支援を続けるNGO「ペシャワール会」(福岡市)が,2010年以来16年ぶりにハンセン病患者の診療にあたるという。ハンセン病診察は、19年にアフガンで武装集団に倒れた現地代表で医師の中村哲さん(当時73歳)にとって「原点」と言える事業です。
今年8月末のM6の大地震を受けて優先させた被災者への支援活動jが落ち着き次第、26年初めに診療を再開する考えのようだ。
福岡市のNGOペシャワール会は、長年、現地の支援活動を続けてこられたが、筆舌に尽くし難い苦労の中で、医療・灌漑・農業の支援を長期間継続し、乾燥地帯を灌漑により緑化し、麦や果物の生産を通して住民の生活の向上に寄与するとともに、医療にも貢献してきた、世界に類のない、世界に誇れる、「日本の海外支援事業」である。
是非とも「ペシャワール会」の活動をご理解を頂き、可能な支援を頂けるとありがたいと思っています。ペシャワール会はインターネットで検索できるので、関心のある方は、是非ともWEBをのぞいてみてください。このような、「日本人による優れた海外支援活動」があることを是非とも知っていただきたいと思っています。
中村さんの『誰もしたがらない、誰も行きたがらないから我々が行く』という精神は確実に受け継がれている。