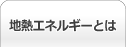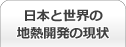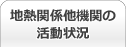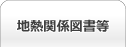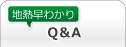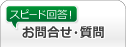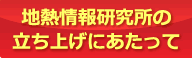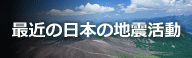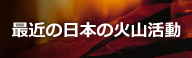地熱情報研究所
2020年3月5日 当研究所(関東南部 埼玉県狭山市)で継続観測中の1m深地温は着実に上昇中。3月3日11.77℃、4日11.87℃、そして本日5日12.00℃。昨年の同日の11.00℃に比べ何と1.00℃も高い。今冬は、地温観測から見ると、観測開始以来8年間で、明瞭に最高地温を継続し、暖冬を数値でよく表現している。
2020年3月3日 桃の節句。晴れで、風もない好天。 当研究所で継続観測中の1m深地温であるが、低下・停滞を小刻みに含みながらも確実に上昇モードに入ったようだ。2月26日11.57℃、27日11.61℃、28日11.57℃、29日11.49℃、3月1日11.51℃、2日11.64℃、本日3日11.77℃。庭では水仙が咲き誇り、大きなピンク色の椿の花も見事だ。黄色い花の小さな草(福寿草?)も咲きだしたようだ。また、思いがけず、まだ暗い早朝、猫の恋の季節のスイッチが入ったようだ。いずれも本格的な春真近かを思わせる。
2020年2月28日 継続中の1m深地温観測であるが、順調に上昇モードにあったが、今日28日一転低下した(2月24日11.30℃、25日11.46℃、26日11.57℃、27日11.61℃、そして本日28日11.57℃)。5㎝深地温も前日より低下した(27日5.5℃、本日28日3.1℃)。地温低下が続くか? 春は足踏みか?
2020年2月26日 当研究所(埼玉県狭山市)が継続している所内での1m深地温観測であるが、どうやら今冬の最低地温(2月12日9.98℃)を記録後上昇に転じ、途中一時停滞期もあったが(2月19日11.01℃、20日、10.97℃、21日10.95℃)、最近の5日間(22日11.00℃、23日11.13℃、24日11.30℃、25日11.46℃、26日11.57℃)は上昇モードに入っている。地温から見ると確実に春に向かっている模様だ。また、過去8年で、この時期の最高地温を記録している。昨年2019年の同時期(過去7年で最高)より1.5℃程度高くなっている。地表面から地中へ流入する熱量の増加が続いている。
2020年2月19日 日本地熱協会 令和元年度第6回情報連絡会に出席した。議事の研究発表は、「地熱開発技術研究開発の現況と取組み」で以下の3題であった。(1)「2019年度JOGMEC地熱統括部の活動状況」 地熱統括部長 西川信康氏、(2)「NEDO地熱事業紹介~これからの地熱開発へ向けて~」 主任研究員 加藤久遠氏、(3)「産総研福島再生エネルギー研究所での地熱研究の取り組み」 総括研究主幹 兼 地熱チーム 研究チーム長 浅沼 宏氏。
2020年2月15日 当研究所で(埼玉県狭山市)継続観測中の1m深地温はここ2、3日急激に上昇した。一昨日2月13日9.98℃、昨日14日10.14℃、本日15日10.46℃。また、この日の地温としては、2013年以降最高となった。
2020年2月13日 若手の地熱事業者と日本の地熱開発に関する情報交換を行った(研究所)。小規模の地熱発電所をすでにいくつか立ち上げ、さらに20近くの案件を抱えているようで、地元との共生を基本として進めており、地熱事業も若手の事業者が育ちつつあり、心強く感じた。基本的な考え方や開発の進め方も堅実であり、今後の活躍を期待したい。
2020年2月9日 継続観測中の1m深地温だが、上昇モードに転じたように見えたが2月6日以降低下に転じた。2月6日10.65℃、7日10.61℃、8日10.43℃、本日9日10.25℃。このトレンドは昨年の同時期とよく似ている。冬の最後の抵抗か。
2020年2月8日 当研究所では1m深地温の継続観測をしているがここ数日の寒気の入り込みに対応し(気象庁の最寄り観測点の最低気温は2月5日-0.1℃、6日-1.7℃、7日-4.3℃)、1m深地温は上昇モードがみられてきたが、低下モードに転じた(2月5日10.66℃、6日10.65℃、7日10.61℃、8日10.43℃)。春を感じるのはもう少し先か。庭にはジョウビタキ来る。
2020年2月2日 当研究所で2012年5月8日以降継続している1m深地温であるが1月30日(10.11℃)以降、3日続けて上昇しており(1月31日10.37℃、2月1日10.60℃、2月2日10.65℃)、上昇モードに入ったか。観測開始以降同時期では最高地温を示している。ただし、今朝の気温は低いようで霜が降りて、5㎝深地温は2.5℃と低かった。
2020年2月1日 当研究所(埼玉県狭山市)で継続観測中の1m深地温は一昨日1月30日10.11℃、昨日1月31日10.37℃、そして本日2月1日10.60℃と急激に上昇している。春の地温上昇モードにはいったか。ただし、今朝は寒く、5㎝深地温は急激に下がっている(前日1月31日6.2℃、本日2月1日2.6℃)。
2020年1月27日 当研究所(埼玉県狭山市)で継続観測をしている1m深地温であるが、昨日やや上昇トレンドも見えたが、本日(10.60℃)は前日(10.61℃)より0.01℃下がった。なお、1月23日以降本日までは、2013年以降の最高地温を記録している。そろそろ1m深地温は上昇モードに転じるか。ただ、今日の夜から明日にかけて、当地は一時的に雨さらに雪が予測されており、興味深いところである。
2020年1月24日 当研究所(埼玉県狭山市)で継続観測中(2012年5月8日観測開始)の1m深地温は依然低下モードにあるが、本日1月24日の1m深地温は過去(2013年以降)最高地温になっている。以下に経年変化を示す。8.70℃(2013年)、9.35℃(2014年)、9.18℃(2015年)、9.64℃(2016年)、9.12℃(2017年)、9.16℃(2018℃)、10.36℃(2019年)、そして本年10.66℃(2020年)。特に2019年と2020年が高いようだ。1m深地温は、地表面から流入する熱量と地表面から流出する熱量のバランスから決まるが、最近は地中への熱の流入が高まっているようだ。近年の地球温暖化・ヒートアイランド現象の高まりの影響を反映している可能性が高い。
2020年1月22日 日本地熱協会主催の「日本地熱協会 令和2年賀詞交歓会」に出席した(霞山会館)。会場がやや狭かったが立錐の余地のないほどの満員であった(400±100名程度か)。多くの参加者があったのは喜ばしいが、問題は2030年度の国の目標:累積150万kWを達成できるかどうかである。現状からすると、かなりスピードアップしないと目標達成が難しいのではないかと危惧している。達成度が不十分だと、その後の日本の地熱開発に氷河期がやってこないとも限らない。当事者にその認識が見られないのが最大の懸念材料である。松尾八幡平、山葵沢に続く、大型発電所の立ち上げを期待したい。そのためには、国立公園内で良好な資源を多く発見し、事業者が先を競って名乗りを上げる状況を作り出すことが重要だ。関係諸機・事業者の奮闘を期待したい。
2020年1月22日 当研究所(埼玉県狭山市)で継続観測中の1m深地温は低下モードにあったが、本日22日10.88℃、昨日も10.88℃で変化なかった。折しも七十二候では大寒初候に入っているが今季最低地温になるか。明日以降、果たして上昇モードに転じるか。
2020年1月20日(月) 岩手県雫石町西山公民館で開催された地元説明会に出席した。事業者 岩岡重樹氏(滝ノ上温泉郷 「滝峡荘 岩手県温泉利用組合 代表)の『滝ノ上温泉「滝峡荘」改築と小規模バイナリー発電設備の設置について』の基調講演の後、当研究所事務局長野田徹郎により「これからの地熱発電」、引き続き、当研究所代表江原幸雄により「最近の国の地熱政策について」の講演が行われた。温泉関係者からいくつかの質問があったが、いづれも講演者の説明により、関係者の理解は得られたと思われる。今後順調に手続き、発電所建設が行われれば、2021年9月上旬にはバイナリー発電所の運転が開始する予定(発電端出力465kW)。
2020年1月16日 (一社)エンジニアリング協会主催の 2019年度 地熱発電・熱水活用研究会 第5回研究会に出席した。講演は2件あり、1)地熱発電の導入拡大に向けた経済産業省の取り組み(経済産業省 資源エネルギー庁 資源・燃料部 政策課係長 小林史和氏)および、2)富士電機の地熱発電設備建設事例(富士電機 山田茂登氏)。
Institute for Geothermal Information. All Rights Reserved.