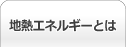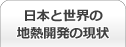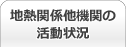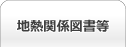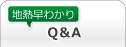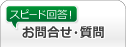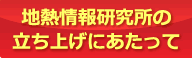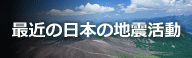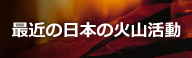地熱情報研究所
6月14日 佐藤 浩・伊藤成輝・佃 十宏氏による「地熱地質調査と生産井掘削ターゲット」(イー・ピックス発行)の寄贈(送付)を受ける。佐藤氏は日本最初の地熱発電所松川地熱発電所の建設に当たった(その後も多くの地熱開発に携わってこられた)地質学者・地質技術者である。現場目線でかつ理論的な背景もしっかりしており、地質分野だけでなく、広く地熱開発に係る技術者必携の書籍と言える。地熱開発において最も関心を持たれる課題に迫った筆者の強い熱意が伝わってくる。広く読まれることを期待したい。近年、技術の継承問題が各産業分野で生じている中、本書は地熱技術開発に携わる人々にとって、まさに継承すべき技術が満載である。購入を希望される方は、インターネットでの申込みをされる場合は、www.gpxshop.com まで。
6月14日 昨日は久しぶりに夏日になり(最寄りの気象庁観測点 所沢で25.4℃)、出かけた都心の日射しもやや強かったが、当地埼玉県狭山市での地温の低下傾向は、やや鈍ったが継続している。19.56℃(昨日6月13日)から19.47℃(本日6月14日)に下がった。このあたりに地温を測ることの意義を特に感じる。1m深地温は地表面から流入する熱量と地表面から流出する熱量のバランスで決まる。
6月12日 経済産業省環境審査顧問会全体会に、顧問(地熱部会部会長代理)として出席した。なお、筆者(江原)は本日任期で退任した(7年6か月)。感謝状を受け、慰労会に出席した。顧問としては、それほど長い期間ではなかったが、本年5月20日に運転開始した秋田県山葵沢地熱発電所(認可出力46199kW)の環境審査に初めから最後まで審査に関わった。地元に受け入れられる発電所を目指して欲しい。また、持続可能な発電を長期間継続してほしい。
6月12日 当研究所(埼玉県狭山市)は所内の敷地で、2012年5月8日以来1m深地温の観測を継続しているが、このところの梅雨時期の雨天・曇天で地中へ入射する熱量に比べ、地中から流出する熱量が多く、長期的に夏に向かって地温が上昇する中、地温が低下を続けている。観測された1m深地温は、6月9日にピーク(20.57℃)を示したが、9日以降、20.46℃(6月10日)、20.16℃(6月11日)、19.79℃(6月12日)と明瞭に低下している。この地温低下傾向は例年みられる。これを過ぎると本当の暑い夏がやってくる。
5月27日 『まだ5月(⇒埼玉県)熊谷で猛暑日』毎日新聞5月27日付朝刊埼玉県版はこう報じている。熊谷地方気象台は26日、最高気温が35.0℃以上の「猛暑日」を熊谷市で今年初めて観測したと発表したという。同気象台によると、統計を始めた1897年以降(5月13日)、1993年に次いで2番目に早い猛暑日となった。26日の県内の最高気温は、8カ所の観測地点全てで今年最高を記録。熊谷市35.0℃、鳩山町35.8℃、越谷市35.1℃、寄居町34.8℃、秩父市34.8℃、久喜市34.1℃、所沢市33.0℃、さいたま市34.2℃-と3カ所で猛暑日となり、鳩山、越谷、久喜、さいたまの4地点は5月の観測史上最高を更新した。熊谷市消防本部によると同日午後3時現在、熱中症の疑いで2人が搬送された。同気象台は、水分を小まめに補給するなど暑さ対策を呼び掛けている。なお、当研究所では2012年5月8日より所内の敷地で1m深地温の観測を継続しているが、2019年5月22日18.42℃、23日18.43℃、24日18.42℃、25日18.43℃とほぼ変化がなかったが、26日18.58℃、27日18.82℃と急激に上昇し、地表面から地中に入る熱量と地表面から流出する熱量の差が急激に増大していることを示している。
5月17日 NHK午前7時のニュースの解説で、「熱くなるか地熱発電」というタイトルで新設の地熱発電所が紹介された。秋田県湯沢市に国内久しぶり(23年ぶり)に大型地熱発電所山葵沢(わさびざわ)地熱発電所(42000kW、約80000戸に供給可能な電力)が今週から、運転開始の報道。今年に入って、岩手県八幡平市の松尾八幡平地熱発電所(7499kW、1月末から運転開始)についで、2カ所目の大型発電所運開である。多くの困難を解決しての運転開始に対して、当該事業者・関係者に祝福と感謝を送りたい。
5月16日 大学で小中高の生徒へのエネルギー教育を担当している方(教授・准教授)の訪問を受けた。学校教育に再生可能エネルギーを体験的に指導する教材(装置)や指導方法を検討してきた方々である。地熱発電の現状や課題を紹介した。地熱発電教育に意欲をお持ちであり、今後、地熱学会・JOGMEC・地熱協会などと協力して、学校教育に取り入れる方向で進むことを期待したい。
5月14日 DIAMOND online 社記者による、当研究所江原幸雄代表インタビュー記事「日本は世界3位の地熱資源大国なのに発電所建設が進まなかった理由」が以下に公開された。https://diamond.jp/articles/-/200086
5月14日 一般財団法人エンジニアリング協会主催の2019年度 第1回地熱発電・熱水活用研究会に出席した。以下の2つの講演があった。1)地熱発電における地域経済付加価値分析とその検証(京都大学経済研究所 先端政策分析研究センター 山東晃大氏)。2)国内外の地熱エネルギーの利用について(エンジニアリング協会 地熱プロジェクト室 副室長 塩崎 功氏)。参加者は約100名で、質疑も活発で盛況であった。
5月8日 当研究所(埼玉県狭山市)敷地内で始めた1m深地温の観測が2012年5月8日以来、丸7年経過し、今日から8年目の観測が開始された。年平均地温は、2015年までは増加傾向であったが(2013年17.47℃、2014年17.37℃、2015年17.70℃)、その後2017年まで低下傾向になり(2016年17.40℃、16.80℃)、また2018年は上昇に転じた(18.28℃)。そして、これまでの全観測期間を線形近似すると、やや低下傾向になっている。観測開始当初、単調な増加を予想したが、長期トレンドを見るにはまだ観測期間が短いようだ。現在観測点は関東一円および秋田市に広がり、合計9カ所12地点に拡大しているが、狭山観測点と同様な傾向が見られる。今後とも各観測点で観測を続けていく予定である。なお、観測結果を公開・議論するために、論文発表や専用のWeb siteを立ち上げる計画をしている(すでに過去4年間、地熱学会や国際学会で、口頭発表、講演要旨発表をしている)。
4月26日 資源エネルギー庁メールマガジン【号外】に、日本地熱協会小椋伸幸会長のインタビュー記事「日本の地熱開発の現状や課題」が掲載されています。以下に紹介します。
『「世界第3位のポテンシャルを持ち、高い技術を有する日本の地熱開発」-小椋伸幸氏(前編)』が資源エネルギー庁メールマガジン【号外】平成31年4月26日(金)発行に掲載された。小椋氏は現在日本地熱協会会長である。主な内容は、「〇長期安定電源として魅力的な地熱、〇世界で活躍する日本の地熱技術、〇地熱に早くから取り組んできた日本、大震災以降再び注目が集まる」 で、地熱エネルギーの活用を推進する日本地熱協会会長の小椋伸幸氏に地熱開発の現状や課題をインタビューしたものです。前後編の2回に分けて掲載されますが、今回は1回目のものです。非常にわかりやすく紹介されています。是非ご覧ください。資源エネルギー庁HPの「スペシャルコンテンツ」からお入りください。
4月23日 都心で開催された、「九大地熱フォーラム」(九州大学OB・OGの在京を中心とした地熱関係者の情報交換会)に出席した。参加者は28名と多く(特に若手が多く)、盛況であった。わが国の今後の地熱開発を託せる期待を感じた。。
4月23日 昨日4月22日は、各地で今季最高気温を示したようなので、当研究所で観測を継続している1m深地温の観測結果についてコメントしておきたい。・・・・・・『東京、大阪、名古屋で夏日 今年一番の暑さ』 毎日新聞4月23日付朝刊はこう報じている。日本列島は22日、高気圧に覆われて西日本を中心に晴れ、気温が上昇したという。高知県四万十市と大分県日田市で30.2℃を記録し、沖縄県を除いて全国で初めて30℃以上の真夏日になったという。東京、名古屋、大阪でも今年初めて25℃以上の夏日となるなど今年一番となる観測点が続出したという。気象庁によると、東京都心部で25.6℃、名古屋市で28.4℃、大阪市で27.6℃を観測し、3大都市圏はそろって汗ばむ陽気となったという。なお、当研究所(埼玉県狭山市)では2012年5月8日以来、所内の敷地で1m深地温の観測を継続しているが、今冬も2月中旬に今季最低地温(14日に9.46℃)を迎え、その後変動を繰り返しながら上昇のトレンドにあったが、4月14日に極小(12.50℃)を迎えた後、単調に上昇を続け、本日23日は、今季最高地温15.09℃を記録した。この間、最寄りの気象庁観測点所沢の平均気温は変動を繰り返しながら、22日には18.5℃と今季最高を示した(なお、22日の最高気温は26.3℃を記録している)。すなわち、地温は、気温に比べ、安定した変化を示し、長期的変化を議論するとき、気温より有利な面があると考えられる。なお、1m深地温は地表面から流入する熱量(日射による熱量)と地表面から流出する熱量(地表面からの渦拡散熱量、地表面からの蒸発熱量、長波放射による地表面からの熱量)の収支から決まるものであり、気温と相関はあるがやや意味するところは異なり、ヒートアイランド現象や地球温暖化をモニタリングにはより有効な観測量と考えられる。
4月19日 地学雑誌からのお知らせニュース(No.26,2019/4/19 )が届きました。当研究所代表江原が3月15日に開催された「第310回 地学クラブ講演会」での講演概要が紹介された。講演題目は「最近のわが国の地熱発電の進展と持続可能な地熱発電技術」。地学雑誌、120巻第1号、地学ニュース、N8。
4月19日 新設(本年1月29日営業運転開始)の本格的地熱発電所「松尾八幡平地熱発電所(岩手県八幡平市)、岩手地熱株式会社」の開所式・安全祈願祭・祝賀会に出席した(外部からの地熱関係者・県及び市・地元関係者の出席者は80名を超え、当該企業関連の参加者を含め100名を超える盛況であった。前日の雨も晴れあがった青空の中、5合目以上には雪が見られる八幡平火山がくっきり見え、天も祝福しているようだった)。わが国における大規模地熱発電所としては22年振りということで、今後のわが国の地熱発電所建設に大いに刺激を与えるものと考える。長年にわたる関係者の御苦労・御尽力に心から感謝を申し上げたい(筆者江原の個人的思いであるが、教え子の九大地熱研究室出身の技術者が重要な貢献をしたことも特に喜ばしく思っている)。本地熱発電所はフラッシュ式で、発電出力7499kW、送電電力7000kW(一般家庭15,000世帯の電気供給に相当)、タービン入口圧力0.35MPaGである。なお、気液比は3~4:1で熱水に比して、蒸気が多い性状である。生産井(3本)の深度1801~2050m、還元井(2本)の深度900~1316m。タービンは国産で三菱日立パワーシステムズ(株)製。蒸気は余裕があるようで、今後長期にわたって安定した発電「持続可能な地熱発電」を実現してほしいものである。若い技術者も新規発電所の立ち上げに立ち会えてみな誇らしく見えた。安定発電を続けるとともに、次の発電所建設に向かってほしい。
4月17日 地熱研究会主催の「平成30年度 第3回地熱研究会」に出席した。講演は以下の3件が行われた。1)「諸外国の地熱発電の現状と推進政策」(西日本技術開発(株)特別参与 金子正彦氏)、2)「還元熱水高度利用化技術開発(熱水中のスケール誘引物質の高機能材料化による還元井の延命・バイナリー発電の事業リスク低減)成果概要のご紹介」(地熱技術開発(株)事業統括部 部長代理 佐藤真丈氏)、3)「温泉モニタリングの関連研究」(産総研 福島再生可能エネルギー研究所 再生可能エネルギーセンター 副研究センター長 安川香澄氏)。いずれも時宜を得た講演内容で、活発な討論が行われた。
4月13日 今日は一冊の図書を紹介したい。「エネルギー資源の世界史-利用の起源から技術の進歩と人口・経済の拡大-」(一色出版、松島 潤編著、2019年4月20日発行 初版第1刷455ページ)。本書「はじめに」の記述を紹介する。「本書は、現代のエネギー資源の問題がどのような経緯で生まれ、どのような点が問題の核心となっているのかといった疑問に答えるように、現代の地球規模でのエネルギー資源問題に関連する技術発展史を、その背景となった社会・経済や貢献度の高かった人物のエピソードにも触れて解説している」。なお、本書第12章には「地熱エネルギー」(372~410㌻)が紹介されている。執筆者は電力中央研究所地球工学研究所主任研究員の窪田健二博士。同氏は九州大学地球熱システム学研究室出身の若手研究者である。・・・・・まれにみる10日間という長い今年のゴールデンウイーク。是非ともこの機会に、普段あまり触れることのない「エネルギー資源の世界」を散歩してみては如何でしょうか。十分な頭の体操にもなると思います。
4月10日 日本地熱協会の2019年度第1回情報連絡会に出席した。議題は以下の3件であった。
(1)自社紹介(中部電力、JX金属探開、エクイスジオエネルギー)、(2)地熱開発現場の近況報告(①阿女鱒岳地域(出光興産))、②ルスツ地域(大林組)、③鹿部地域(SBエナジ・大阪ガス)、④大崎市高日向山地域(電源開発)、⑤湯の谷地域(レノバ)、(3)運営委員会及び専門部会報告(なお、この中で、当研究所NPO地熱情報研究所が今年度より、理事会により、特別会員に認められたことが報告された。来月5月29日に開催される地熱協会総会で正式に承認される運びになっている)
Institute for Geothermal Information. All Rights Reserved.