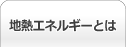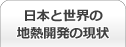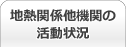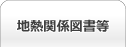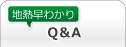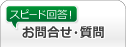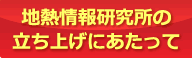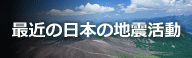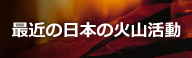2023年7月5日午後、2023年6月30日(金)13:00~16:15 に行われた産総研 福島再生可能エネルギー研究所(FREA)による2023年度研究報告会のアーカイブ映像配信のプログラムを見た。内容は以下の通りであった。13:00~13:05 主催者あいさつ(上席執行役員兼エネルギー・環境領域 領域長 小原春彦氏)、13:05~13:10 来賓あいさつ(福島県副知事 佐藤宏隆氏)、13:10~13:15、来賓あいさつ(郡山市長 品川萬里氏)、13:15~13:50 基調講演 再生可能エネルギー政策について(経産省 資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 新エネルギー課 課長補佐 津田健人氏、13:50~14:15 講演(「福島県再エネ研究会10年の歩み」と「FREAと連携した県内産業育成の取り組み」の紹介(エネルギー・エイジェンシーふくしま 代表 服部靖弘氏)、14:15~14:30 FREA紹介 福島再生可能エネルギー研究所の概要紹介(産総研 福島再生可能エネルギー研究所 所長 宗像鉄雄氏)、14:35~15:10 再生可能エネルギー研究センター概要紹介 主力電源化に向けた利用拡大およびO & M(技術開発 産総研 再生可能エネルギー 研究センター長 吉田郵司氏)、15:10~
15:40 カーボンニュートラル実現に向けた次世代エネルギーネットワーク技術(エネルギーネットワーク、水素関係) 産総研 再生可能エネルギー研究センター副研究センター長 難波哲哉氏)、15:40~16:10 適正な導入拡大のための研究開発、データベース構築(地熱・地中熱関係 産総研 再生可能エネルギー 副研究センター長 浅沼 宏氏)、16:10~16:15 閉会あいさつ 産総研研究戦略企画部 次長 兼 福島再生可能エネルギー研究所 所長代理 古谷博秀氏。 ⇒FREAにおける「地熱・地中熱を含めた再生可能エネルギー全般の最新研究」が紹介された。特に印象に残ったのは、FREAの最新研究・スタッフが確実に地元企業に浸透し、地元の技術の進展に実に大きな貢献をしていることだった。実によい実例と感じた。各都道府県レベルでも、核となる研究機関と地元企業の強い結びつきは可能である。そのような中核の研究機関と地元自治体の強力な連携ができれば、日本の再可能エネルギーも飛躍的な増加が期待されるのではないか。